中国胡琴音楽古典譜 阿炳 - 二胡弦堂
中国胡琴音楽古典譜 阿炳
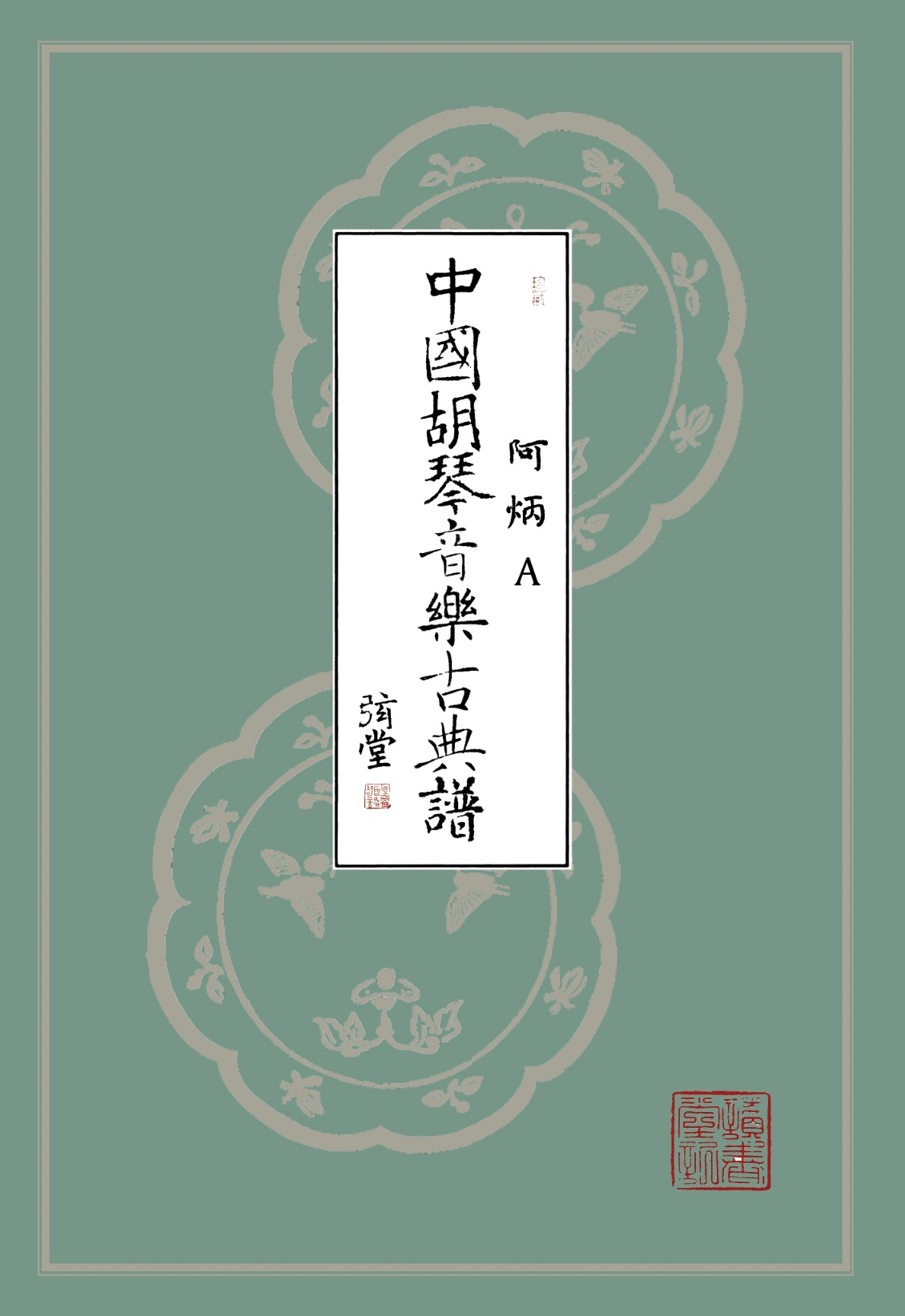
華彦鈞[huā yàn jūn]は無錫出身の演奏家で、盲人を意味する「阿炳[āh bǐng]」という名でよく知られています。残された唯一の録音は50年9月2日19時半から中国音楽研究家・楊蔭瀏によって胡琴3曲、琵琶3曲が収録されました。本書では胡琴作品3曲《二泉映月》(er-quan-ying-yue)、《聴松》(ting-song)、《寒春風曲》(han-chun-feng-qu)を所収致しました。
阿炳は道教道士でしたが盲目になり、乞食となって、無錫の街を練り歩いて生計を立てていたとされ、苦しみと孤独のうちに数曲の作品を残して亡くなったとされています。
しかし若い中国人研究者たちが、この見解に疑問を抱くようになり、数々の反証を挙げるようになりました。その結果、阿炳が盲目になったのは確かであるものの、その他の点については真逆だったということが明らかになってきました。
3頁以上の作品は演奏中に頁をめくる必要がないように2分冊とすることで同時に開けるようにしました。曲の1ページ目は必ずA巻の方に置き、B巻でも同じページに置くことで目次を参照する必要がないようにしています。本は開きっぱなしにするのが難しいので冊子とし、最大ページ数が40なのでこれで制作しています。
阿炳は盲目になったことによって収入が減少した可能性はありますが、依然として裕福(演奏の謝礼を要求しないのはもちろん、自分から無償で請け負うことも多々あり)。生涯、道教住職として過ごし、亡くなるまで街の名士だった(住まいも生涯変わらず)。愛妻家で、阿炳が亡くなって29日後に祭奠を行ったその日に妻も亡くなった(自殺で後を追った可能性が高い)。交友範囲は非常に広く、当時最高の演奏家たちと頻繁に演奏していた。積極的で学習意欲が高く、明るい性格だった。情の深い人だった。しかし楽団を組むなど群れることはなかった。 生前から有名だった。街を練り歩いていたのは社会風刺と批判を行うためで、おそらく収入はなし、公益のためだった。比較的恵まれた生涯で、幸福だった。
生前から有名だった。街を練り歩いていたのは社会風刺と批判を行うためで、おそらく収入はなし、公益のためだった。比較的恵まれた生涯で、幸福だった。
ということがわかってきました。本書は楽譜ではありますが、これらの背景は非常に重要と考え、新旧それぞれの情報を検討して(以前の見解でも正しい部分はある)、まとめることにしました。特に重要なのは阿炳が道教道士だったことです。古代の道士は必要な時に法事を行う以外は基本的に農民で、様々な民謡を集めて収集する人々でした。旅行者が持ち込む作品を紙にまとめて保管していました。祭祀に役立てるためですが、その結果、世俗と宗教音楽の区別がほとんどなくなっていました。道教があったから音楽も保存されていました。そして宗教が衰退した時、かつての道士たちは国立楽団に加入し、中国音楽とは何かを規定しました。
つまり、阿炳の生涯は、中国音楽がどういうものなのかを示すものでもあります。これまでの出版も「うんちく本ではない」とは言いながら、楽譜としては情報量が多いものでした。ある程度の関係情報は必要だからです。本巻はおそらく一番うんちくが多いものになりそうです。
録音への入域は、どちらも「cyada.org」です。
| 二泉映月 | 50年作曲者自演録音 | 蒋風之教授其子蒋巽風 参考資料:酔仙戯1 酔仙戯2 返魂香 |
|---|---|---|
| 聴松 | 50年作曲者自演録音 | |
| 寒春風曲 | 50年作曲者自演録音 |
