二胡に二泉弦を使う - 二胡弦堂
 できれば専用の琴の方が良いですが、使えると思います。二泉胡は通常、琴胴が2mm大きく作られています。もしくは中胡を使うこともできます。しばらく使われてきた二胡にこれまでと異なる弦を張ると楽器の響きが合わない感がありますが、強振させるとすぐに馴染んできます。そのためすぐに判断しないことが重要です。
できれば専用の琴の方が良いですが、使えると思います。二泉胡は通常、琴胴が2mm大きく作られています。もしくは中胡を使うこともできます。しばらく使われてきた二胡にこれまでと異なる弦を張ると楽器の響きが合わない感がありますが、強振させるとすぐに馴染んできます。そのためすぐに判断しないことが重要です。
1950年に阿炳が「粗弦」を使って演奏録音、これは老、中弦、つまりGとD弦で、今で言う二泉弦か中胡弦、無錫の奏者のほとんどは粗弦で演奏したとされています。この時代の粗弦は「高手」上級の奏者が使うものとされていて、対して「細弦」中、子弦、現代二胡のDA弦は、一般の奏者が扱うものでした。そのため、周少梅、劉天華ら黎明期の教育者たちは生徒にDA弦を使わせました。
阿炳の録音を行った天津音楽学校(現・北京中央音楽学院。劉天華による創立)の研究者たちは、阿炳が粗弦で雑音無く美しい音で演奏できるということに驚いたようです。 彼らは、細弦でないと綺麗な音が出ないと考えていました。それで、阿炳に「あなたはどうして粗弦を使うのですか」と質問しました。すると彼は「耐久性が違うから。もし外弦が切れて、弦がなくなったら、外弦にも老弦を張っていました。音もこの方が濃厚な音が出ますから」というように回答したそうです。確かに太い弦は耐久性がありますが、扱いは難しくなります。それでも濃厚な音を求めて太い弦に向かう傾向だったことがわかります。
彼らは、細弦でないと綺麗な音が出ないと考えていました。それで、阿炳に「あなたはどうして粗弦を使うのですか」と質問しました。すると彼は「耐久性が違うから。もし外弦が切れて、弦がなくなったら、外弦にも老弦を張っていました。音もこの方が濃厚な音が出ますから」というように回答したそうです。確かに太い弦は耐久性がありますが、扱いは難しくなります。それでも濃厚な音を求めて太い弦に向かう傾向だったことがわかります。
無錫の伝説的名手・沈養卿(1884-1956年)も阿炳と同様、粗弦の使用者でした。1910年代の最も高名だった京胡の名手 "南北二陳" で知られる "南陳"こと陳公坦が使っていた二胡は、壇木製でこれにも粗弦が使われていたと言われています。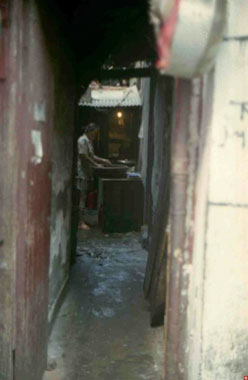 無錫道士(阿炳は盲目になる前、道士だった)が、十番鼓(梵音)、十番锣鼓を演奏する時、使う二胡には、粗弦が必ず使われました。
無錫道士(阿炳は盲目になる前、道士だった)が、十番鼓(梵音)、十番锣鼓を演奏する時、使う二胡には、粗弦が必ず使われました。
江南地方の二胡については、今では鉄道で10分あまりの距離しか離れていない都市間ですら、規格や使う素材に相違があります。それぞれの都市に独自の二胡があります(これは地方の伝統劇の伴奏と密接な関連があります)。
そこで、無錫製と思われる古い二胡を入手してみました。これは胴が竹製でした。内部の容積も普通よりかなり大きかったので二泉胡として使えそうに思えました。しかしどうしても細弦の方が響きが良かったので、容積だけでは判断できないように思えます。胴がかなり小さい高胡のような楽器でも音が低いことがあります。昔の楽器は規格が統一されていないので分からないことが多々あります。さらに京胡は音の高い部分が目立つ楽器ですが、使う弦は粗弦です(京胡は低い音の成分がかなり含まれています)。
西洋の弦を使うという奏者もいます。バッハ「無伴奏チェロパルティータ第6番」を演奏するための楽器で「チェロ・ピッコロ」と呼ばれる調弦が5度高い小型のチェロに使われるE,A弦の転用は可能とされています。ダダリオ(D'Addario・米)社がヘリコア(Helicore)という製品名で出しており、極細のスチール線を撚り合わせた心材に、アルミやチタン等の金属箔を巻き付けた物とのことです。弦のゲージではビオラ弦で代用可能ですが、長さが足りないのでチェロ・ピッコロのE線を使うという選択です。
